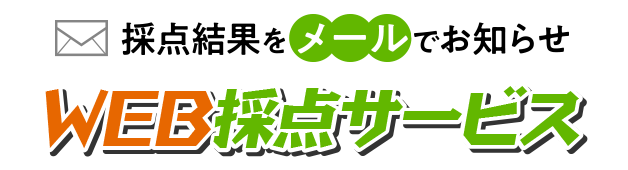1級造園施工管理技士 解答速報

一次検定
実際の試験で解答した番号と必要事項を入力してください。
当学院ホームページで「WEB採点」し、採点結果をメールにてお知らせします。
WEB採点サービスは終了しました
1級造園施工管理技士 二次検定対策
無料1級造園施工管理技士
二次検定ポイント講習会
1級造園施工管理技士の資格を取得するために必ず合格しなければならない二次検定。しかし記述式問題は年々難易度を増しており、二次検定に合格するためには、そうした記述式問題にしっかりと対処しておくことが必要となってきています。
そこで、日建学院では合格への鍵となる二次検定ポイント講習会を「無料」にて全国で開催します。
参加された方には「1級造園二次検定分析資料」をプレゼント致します。是非ともこの機会にお申込み下さい。
![]() 1級造園二次検定分析資料プレゼント
1級造園二次検定分析資料プレゼント

| 内容 | ・記述式問題の分析と対策 ・二次検定の学習方法のアドバイス ※解説時間(約30分) |
|---|---|
| 開催日程 | 開催日程一覧(PDF) |
無料二次検定 解答試案プレゼント!
 ご希望の方全員にもれなく差し上げます!
ご希望の方全員にもれなく差し上げます!
日建学院では、ご希望の方に2024年度1級造園施工管理技士二次検定の「日建学院オリジナル解答試案※」を差し上げています。
※解答試案について
解答試案は当学院が独自に行うものであり、試験実施機関である一般財団法人 全国建設研修センターとは一切関係がありません。
1級造園施工管理技士
二次検定対策講座
二次
| 概要 | |
|---|---|
|
初学者・学習経験者対象
二次コース |
二次検定に特化した集中対策講座年々難易度の高い問題になってきている「記述式問題」対策を第一に、短期間で試験のツボを押さえて難関試験突破を目指します。 |
総評
出題の概要
問題A・問題Bとも、出題数・解答数・解答方式に変更はありませんでした。
問題Aと問題B(問題1~23)は、四肢択一式のマークシート方式で行われました。問題B(問題24~29の6問)は、施工管理法(応用能力問題)として、四肢多択式のマークシート方式で行われました。
| 試験時間 | 出題数 | 解答数 | |
|---|---|---|---|
| 問題A | 150分 | 36 | 36 |
| 問題B | 120分 | 29 (このうち 応用能力問題:6) |
29 (同左) |
出題の内容
【問題A:例年より、やや易しいレベル】
出題の多くは近年の過去問題がベースになっており、高得点を獲得できた受検者も少なくないと思われます。
[問題1]日本庭園、[問題3]土壌、[問題10]木材の一般的な性質、[問題15]水準測量、[問題23]擁壁、[問題24]排水工、[問題32]工程・原価・品質の関係図などは頻出問題であり、必ず正解しておきたい問題でした。
一方、[問題7]造園樹木では、実の色・花の色に加え、針葉・広葉、常緑・落葉という葉族の種類まで判断する難易度の高い問題であったと思われます。
[問題25]の茶室の平面図は、平成29年以来の出題でした。「にじり口」は、近年も出題されている用語ですが、茶事を準備する場所=「水屋」と判断できたかがポイントでした。
[問題36]のネットワーク式工程表は、トータルフロートまで問われているため、最早開始時刻と最遅完了時刻を正確に計算する必要がありました。
【問題B:問題1~23、問題24~29共に、例年より、やや易しいレベル】
問題Bについても、近年の過去問題がベースとして出題され、[問題3]出来高累計曲線、[問題5]公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の用語の定義、[問題8]統計量の計算、[問題13]建設機械等を使用する作業の資格などは、得点しやすい問題でした。
[問題7]植栽基盤の調査は、与えられた数値が植栽基盤として適しているかどうかの良否を問う出題が近年は続いていましたが、平成30年度以来、数値の組合せを問う問題が出題されました。得点するには、S値及び最終減水能の判断基準となる数値を正確に覚えておく必要がありました。
[問題14]移動式クレーン作業の正答肢は初出題の内容でしたが、つり荷の下は立ち入り禁止とする現場での原則に従えば、正答を導くことは容易であったと思われます。
問題24~29の応用能力問題は、四肢の中から "適当なものを全て選ぶ" 四肢多択式であることから、一肢一肢の正確な正誤判断が必要な難易度が高い出題形式です。
[問題24]耐陰性が優れている樹木は、樹木に関する正確な知識がないと判断が難しい問題でした。
[問題25]、[問題26]、[問題27]、[問題29]には、近年出題されている内容も多く出題されていましたが、新規出題の選択肢も含まれており、得点するためには、過去問題以外の造園施工に関する基本的な知識も必要でした。
なお、[問題28]公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の合否判定の計算は、毎年出題されている問題であり、確実に得点したい問題でした。
応用能力問題で、合格基準をクリアすることが、今年度も合否の分かれ目になると思われます。
合格発表
一次検定の合格発表日は令和7年10月9日(木)で、近年の合格基準点と合格率は、次表の通りです。合格基準は全体の得点が60%(39点)以上、かつ、施工管理法(応用能力)の得点が30%(2点)以上と公表されています。ただし、試験の実施状況等を踏まえ変更される可能性もあります。
| 年度 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格基準点 | 全体 | 39 | 39 | 39 | 38※ | 39 |
| 応用能力 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 合格率(%) | 39.6 | 35.9 | 44.0 | 35.2 | 45.4 | |
※R05は基準点の引き下げ有
公表されている合格基準をクリアされた方は、早めの二次検定準備をお勧めします。
お気軽にご相談ください
日建学院コールセンター
0120-243-229
受付時間 10:00~17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)