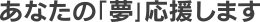宅建試験の合格率とは?
合格率が低い理由について解説!
宅建士の取得を目指している方にとって合格率は気になるところです。実際、宅建試験の合格率は、15~18%とそれほど高くはありません。そこでこの記事では、
「宅建試験の合格率はどれぐらい?」
「宅建試験の合格率が低い理由は?」
と悩んでいる方のために、宅建試験の合格率・合格率が低い理由・合格ライン・合格するメリットについて紹介します。宅建試験受験を考えている人はぜひ参考にしてください。
目次
- 宅建試験の合格率
- ■宅建試験の合格率推移
- ■宅建試験の合格基準点
- 宅建試験の合格率が低い理由
- ■受験資格に制限がない
- ■出題される範囲が広い
- ■勤務先から指示されて受験している
- 宅建試験の合格ライン
- ■権利関係
- ■宅建業法
- ■法令上の制限
- ■その他関連知識
- 宅建試験に合格するメリット
- ■不動産業界などで採用されやすい
- ■不動産業界で必須の資格である
- ■不動産の売買で役に立つ
- ■就職や転職に強い
- ■法廷講習会の受講で更新できる
- ■専門性や職域を広げられる
- ■女性に有利な資格である

宅建試験の合格率
宅建試験の合格率は高いわけではなく、例年15~18%です。ここから宅建試験の合格率について詳細に見ていきましょう。
宅建試験の合格率推移
上図は過去10年分の宅建試験合格率の推移を表したグラフです。受験者数の増減に関わらず常に15~18%台の推移となっています。例年20万人以上の方が受験されるので、毎年宅建試験の上位約3万人~4万人の方が合格者となり、約17万人前後の方が不合格者ということになります。
宅建試験の合格基準点
宅建試験の合格基準点の特徴は、合格ラインが変動する方式(相対評価)を採用していることです。基本的な合格ラインを決めて、受けた人全員の点数から合格基準点をはじき出します。毎年合格基準点が変動し、受験者の得点で上位約15~18%(約3万人~4万人)が合格となる仕組みです。そのため、何点取れたかという点数だけ見るのではなく、上位15~18%に入るという合格率を考えて勉強するようにしましょう。
宅建試験の合格率が低い理由
上述したように宅建試験は合格率が高いわけではありません。なぜ宅建試験の合格率は低いのでしょうか?ここから理由について詳しく見ていきます。
受験資格に制限がない
建築士やFP2級には受験資格が必要ですが、宅建士は受験資格に制限がありません。また、受験手数料も8,200円と手ごろな費用で受験することが可能です。受験資格制限がないので、何度でも受験できるといった気軽さもあります。そのため、勉強が不十分なまま試験を迎える人が多いことが、合格率が低い理由の一つです。
出題される範囲が広い
宅建試験は「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」「その他関連知識」から出題され、幅広い勉強が必要です。近年は水害ハザードマップの記載条項など、専門的な知識を求める問題も追加されているだけではなく、試験内容も難しくなっています。丸暗記で勉強するだけでは、合格が難しい試験になってきています。
勤務先から指示されて受験している
宅建試験受験者には勤務先から指示されて受験している人が多くいます。不動産会社は、一定数の宅建士を社内に設置しなくてはなりません。物件の売買は、宅地建取引業法・民法、建築基準法などが関係しているため、宅建士以外の人が重要事項の説明を行うことは禁じられています。そのため、不動産会社は社員に宅建士の取得を義務付けている事が多いのです。しかし、日々の業務に追われ十分な勉強ができないと、不合格といった結果になるでしょう。
宅建試験の合格ライン
宅建試験の合格ライン(合格基準点)は受験者全体の得点が低い場合は下がり、得点が高い場合は上がります。出題数は50問ですが、近年の合格ラインは34~38点と変動しています。また、宅地建物取引業で働いている人は「5点免除制度」があります。「5点免除制度」は、宅地建物取引業に従事していると「その他関連知識」の「5問免除科目」の5問が免除される仕組みです。しかし、免除制度を利用するには宅建登録講習の受講・修了が必要になります。
ここから、宅建試験各科目の目指すべき合格ラインについて詳しく解説します。
権利関係
「権利関係」は出題数が14問と多いため重点的に勉強する必要がありますが、特に民法は1,000以上の条文があるため、丸暗記は困難です。また、専門用語が多いだけではなく、裁判例の出題も増加傾向にあります。丸暗記ではなく、しっかりと法令等を理解しながら勉強することが重要です。
重点的に勉強する必要があるのは、以下の項目です。
- ・制限行為能力者
- ・意思表示
- ・代理
- ・時効
- ・物権変動
- ・不法行為
- ・相続
- ・賃貸借及び借地借家法
- ・区分所有法
難易度が高く丸暗記も厳しいため、合否に影響する基本的な項目だけを確実に押さえ8点取ることを目指しましょう。
宅建業法
「宅建業法」は宅建試験の4割(20問)が出題される最重要科目です。また、条文が少ないため全ての項目が重要です。この科目は満点を取る受験者も多いので、念入りに学習しなくてはなりません。ひっかけ問題が多く、宅建業法に関わる法律の理解が絶対に必要な科目ですが、例年、2~3問程度の難問以外は必ず得点が可能な出題ばかりです。
そのため、重点的に勉強する必要があるのは、
- ・全範囲
宅建業法は合格のカギを握る科目ですので、合格するために18点取ることを目指しましょう。
法令上の制限
「法令上の制限」とは、建築基準法、都市計画法など不動産の制限に関する内容で、8問出題されます。重要なポイントは過去に繰り返し出題されており、権利関係、宅建業法とともに「主要3科目」と言われていますが、特に専門用語や数値等の暗記の占める比重が大きく、実は苦手とする方が多い科目です。しかし、例年、合格者と不合格者の差が最も大きい科目でもあり、合格者は法令上の制限で確実に得点を稼いでいます。
重要な項目は下記の通りです。
- ・都市計画法
- ・建築基準法
- ・盛土規制法
- ・土地区画整理法
- ・農地法
- ・国土利用計画法
それぞれの法令の根拠をしっかりと理解して、合格するために6点取ることを目指しましょう。
その他関連知識
「その他関連知識」では「税法・価格の評定」で3問、「5問免除科目」で5問の合計8問が出題されます。
税法・価格の評定で重要な項目は下記の通りです。
- ・不動産取得税
- ・固定資産税
- ・印紙税
- ・登録免許税
- ・地価公示法
- ・不動産の鑑定評価
税法・価格の評定は例年難易度が高い傾向があります。毎年改正される税法の改正点を抑えるなどで1~2点を取ることを目指しましょう。
「5問免除科目」で重要な単元は下記の通りです。
- ・住宅金融支援機構
- ・景品表示法
- ・統計
- ・土地
- ・建物
5問免除科目は一般常識を含めた非常に幅広い範囲から出題される為、効率的な学習が非常に難しい科目です。過去問題を中心に絞り込んだ学習をする、日建学院の改正法セミナーなどに参加し予想問題を入手するなどで4点取ることを目指しましょう。

宅建試験に合格するメリット
宅建試験に合格するメリットは、不動産業界などで採用されやすい、不動産の売買で役に立つ、就職や転職に強いなどです。そのため、子育てなどで仕事を辞めた主婦の方などにも根強い人気があります。ここから、宅建士を取得するメリットについて詳しく見ていきましょう。
不動産業界などで採用されやすい
上述したように、不動産売買において重要事項の説明には宅建士が必要です。そのため、不動産業界では宅建士の資格取得者が有利になります。資格を保有していると、会社から5,000~30,000円の資格手当てが支給されるケースが多いです。収入アップを目指す人には欠かせない資格でしょう。
不動産業界で必須の資格である
宅建士は不動産業界には必須の資格です。不動産は高額商品であり、不動産取引の最終段階で、重要事項の説明をしなくてはなりません。そのため、宅建業者は一定の人数の専任の宅建士の設置が必要です。宅建業者が宅建士を設置しなかった場合、法律違反となり業務停止処分の対象となります。そのため、不動産業界では宅建士を重視しているのです。
不動産の売買で役に立つ
宅建士の資格は不動産業で役立つだけではなく、マイホーム購入や相続など、自身が不動産を取得する時も役立ちます。取得のメリットは、民法など様々な法律を学べるため、トラブルを避けられることです。
就職や転職に強い
宅建士は、不動産業だけではなく、金融業や建設業にも強い資格です。実際に合格者の中には、金融業や建設業の方が多くいます。そのため、資格を持っていると転職の際、有利になると言えます。特に建設業の場合、建築士と宅建士の資格を両方持っていると、土地探し・建物の設計・税金の手続きなど様々な場面で力を発揮できます。
法定講習会の受講で更新できる
宅地建物取引士証は、法定講習を受講することで更新できます。有効期限は5年間で、更新を希望しない場合、宅建士証を返納する必要がありますが、再度講習会を受講すると交付を受けることができます。宅建試験の合格実績は無期限となります。つまり、宅建試験の合格(宅建士資格)は一生有効ですが、宅建士証は有効期限があって更新が必要になります。
専門性や職域を広げられる
宅建士の資格は専門性が高く、資格手当をもらえるケースが多いため、普通のサラリーマンより年収が高くなります。また、法律で設置が義務付けられているため、不動産業界にいると昇進しやすくなるのがメリットです。年収アップやキャリアップには欠かせない資格でしょう。
女性に有利な資格である
宅建士資格は、出産で会社を退職する可能性がある女性にとって有利な資格です。宅建士の資格を持っていると社会復帰しやすくなります。主婦の経験を活かし、不動産売買において、ファミリー層に適切なアドバイスをすることも可能です。宅建は女性が再就職を考える上で転職の武器となるでしょう。
まとめ
宅建試験の合格率は高いわけではなく、15~18%の水準で推移しています。宅建試験の合格率が低いのは、受験資格に制限がない、出題される範囲が広いなど様々な理由があります。受験する場合、出題数の多い民法や宅建業法に重点を置き、丸暗記ではなく言葉の深い理解が必要です。宅建士資格を取得すると、不動産業界などで採用されやすい、不動産の売買で役に立つなどメリットは多岐に渡ります。特に女性の場合は出産後に仕事に復帰しやすいといった利点があります。
宅建試験で合格を目指すためには、何点取れたかという点数だけ見るのではなく、上位15%に入るという合格率を考えて勉強するようにしましょう。