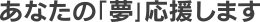宅建試験の理想的な時間配分は?
限られた時間で効率よく解答する方法を解説!
宅建試験では120分の試験時間で50問を解かなくてはいけません。1問につき約2分の時間配分となりますが、近年の宅建試験は問題文や選択肢が非常に長文化傾向となっており、「時間が足りなくなった」という方が多くなっています。そのため、試験の時間配分を意識する必要があり、科目ごと・1問ごとにかけられる時間がどのくらいか事前に理解していなければいけません。
この記事では、宅建試験の時間配分について解説いたします。時間が足りなくて解答できなかったということがないよう、この記事を参考にしてください。
目次
- 宅建試験の内容
- ■宅建登録講習修了者は5問免除
- 宅建試験は時間との勝負
- ■近年の出題形式を把握する
- ■1問2分はあくまでも目安
- ■分かる問題から解いていく
- ■見直しする時間も考慮する
- 科目ごとの出題傾向
- ■権利関係(民法等)
- ■法令上の制限
- ■宅建業法
- ■税その他
- ■5問免除
- 宅建士試験の合格率を高める勉強法
- ■通信講座
- ■資格学校

宅建試験の内容
宅建試験は全50問、四肢択一のマークシート方式の試験です。試験科目は4科目で各科目の出題数は下記となります。
| 試験科目 | 出題数 |
|---|---|
| 宅建業法 | 20問 |
| 権利関係(民法等) | 14問 |
| 法令上の制限 | 8問 |
| 税・その他 | 8問 |
科目ごとの出題数は近年変更されていませんが、合格基準点は年度によって異なります。年度によって34点~38点と差があるため、まずは36点~37点が合格ラインと考えておくと良いでしょう。
宅建登録講習修了者は5問免除
宅建試験には、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習(宅建登録講習)に受講し修了すると5問の免除が受けられる制度があります。
この講習は宅地建物取引業に従事している「従業者証明書」を持つ人のみ受講が認められます。およそ2か月間の通信講座受講と、2日間のスクーリングを行い修了試験に合格すると「登録講習修了者番号」が発行されます。この番号が発行されてから3年間、宅建本試験において、問題の一部(例年問46~問50にあたる5問)が免除されます。
宅建試験は時間との勝負
冒頭にも触れたように宅建試験は時間との勝負です。試験時間内に問題を解くためのポイントをご紹介します。
近年の出題形式を把握する
近年の宅建試験の問題は、過去の宅建試験と比べると問題文や選択肢が長文化傾向にあるとともに、単純な暗記で回答できる問題が減り、何を問われているかの問題文自体の文章を理解・整理する必要がある出題が増えています。
そのため近年の長文化や文章の理解・整理に慣れていないと、そもそも何を問われているのかを読み解くのに時間がかかり、解答時間が足りなくなる恐れがあります。近年の出題形式の傾向を把握するには、近年の過去問を繰り返し解き長文化に慣れておくことが必要です。最初は分からなくても、徐々に問題文や選択肢に書かれている文章の要約をすることが出来るようになります。
1問2分はあくまでも目安
宅建試験では1問にかけられる時間は約2分とお伝えしましたが、これは単純に120分の試験時間を50問の問題数で割った時間に過ぎません。実際に試験に挑むと2分では解けない問題もあれば、1分もかからずに解ける問題もあります。
1問2分はあくまでも目安なので、2分という時間に縛られる必要はありません。得意とする科目にかける時間は少し短くして、不得意な科目は長めに時間をかけるといった柔軟な対応を取り、科目ごとに最適な時間配分をできるようにしましょう。
分かる問題から解いていく
宅建試験では、例年、出題される科目の順番が決められています。しかし、解答する順番が決められている訳ではないので、得意とする科目の問題から解答していきましょう。
宅建試験は権利関係(民法等)から始まります。出題順に沿って解こうとして最初の権利関係が苦手科目だった場合、予想以上に時間がかかってしまった・解けない問題が多いと焦りが生じ、残りの問題も普段は解けるはずの問題が解けない・時間がかかる恐れがあります。
分かる問題から解いていくことで、不安や緊張を和らげることができるので出題順にこだわらず、分かる問題から解いていきましょう。
見直しする時間も考慮する
忘れてはいけないのが、全ての問題を解いた後に見直しを行う時間の確保です。間違いなく、全ての問題に解答したと思っていても、見直しをしないと不安になることがあります。実際に見直してみると「こっちの方が正しかった」「マークシートの転記ミスをしていた」という可能性があります。50問全てを見直すのに15分ほどかかることを想定して、最後に見直しを行うための時間を確保できるようにしましょう。
科目ごとの出題傾向
試験で適切な時間配分を決めるには科目ごとの出題傾向を理解することが重要です。科目ごとの出題傾向を確認しましょう。
権利関係(民法等)
権利関係は勉強するのに苦戦させられることが多い科目です。権利関係の問題は、法律の解釈で正誤が問われる問題や、判決文の要旨が問われるなど様々な出題形式があります。問題文が長く、どこが問題の論点なのかを把握しなければいけないので1問に時間がかかるのも特徴です。
権利関係では「借地関係」「借家関係」「区分所有法」「不動産登記法」この4つはほぼ必ず出題されます。条文を丸暗記することは非常に難しいため、暗記ではなく法律の考え方・意図を理解することが重要です。
法令上の制限
「法令上の制限」の学習範囲はそれほど広くはありませんが、「法令上の数値や条件」などをどれだけ暗記できるかが鍵になります。
「都市計画法の開発許可制度」「建築基準法の集団規定」「盛土規制法」「農地法」「国土利用計画法」「土地区画整理法」この6つをしっかりと暗記するようにしましょう。また、「法令上の制限」は過去問から出題されることが多い科目です。過去問を繰り返し解いて出題傾向が理解できるようにしましょう。
宅建業法
宅建業法は出題数が最も多い科目ですが、学習範囲は出題数に比べると広くはありません。しかし、ほぼ全ての範囲の重要度が高いので、しっかり学習しなければいけません。
特に重要な項目が「重要事項説明」「37条書面」「媒介契約」「その他の業務上の制限」この4つです。実務を行う上でも重要な知識なので必ず覚えましょう。「宅建業法」は難解な法律用語が多い「権利関係」と比べると、難易度は若干下がります。覚える量は多くなりますが、しっかりと頭に詰め込みましょう。
税その他
「税その他」は、4科目の中で最も専門的な知識を問われる場合が多い科目です。
出題されることが多い問題は「不動産取得税」「固定資産税」「地価公示法」の3つです。税は「権利関係」の法律用語と同様に最初は戸惑いますが、宅建士試験で求められているのは税制に関する広く専門的な知識ではなく、不動産取引に特化した知識が出題されますので、しっかり暗記して点数を取れるようにしましょう。
5問免除
講習受講者が免除される問題の学習量はそれほど多くはありません。5問免除問題の「住宅金融支援機構」「公正競争規約」「土地」「建物」全て過去問を繰り返し解くことで対応可能です。ただし、「統計」は最新のデータを確認することを忘れないようにしましょう。
日建学院では「統計の最新データ」を含めた改正法セミナーを毎年開催しています。宅建士試験を受験される方は、ぜひご参加ください。
模試を受けて時間配分を確認する
自宅学習だけでなく、模試を受けて本番の試験を意識しながら時間配分を確認してみましょう。
時間配分は頭で分かっていても試験本番では雰囲気に飲まれてしまい、うまくいかない可能性があります。本番の雰囲気に近い模試を受けることで雰囲気に慣れ、科目ごとの時間配分の確認と、採点も行われるので課題を確認することもできます。
模試は資格学校などで開催されており、資格学校の受講生でなくても数千円の模擬試験代を支払うことで受けることができます。受験方法は主に会場受験・自宅受験の2種類があります。資格学校によって、模試の受験方式は異なるので自分に合う方式を選んで受験し、時間配分と課題を確認して本番の試験に自信を持って挑めるようにしましょう。
日建学院では全国最大規模での「宅建 全国統一公開模擬試験」を実施しています。
本試験での時間配分演習や弱点チェックの為にも、ぜひ受験してみてください。

宅建士試験の合格率を高める勉強法
宅建試験は合格率が20%を下回る難易度が高い試験です。独学で合格を目指すよりも、通信講座や資格学校の活用で合格率を高めることができます。
通信講座
通信講座は自分のペースで勉強を進められるメリットがあります。テキストや映像講義で学習するため、仕事を終えた帰宅後や休日に集中して勉強するなど、学習スケジュールを自分の都合に合わせることができます。通勤や休憩時間も映像講義で勉強できるので隙間時間を勉強時間にすることができます。
デメリットは一緒に勉強する仲間ができないので、モチベーションの維持が難しいことです。この他に講師に質問することはできますがタイムラグが発生しやすく、スムーズな勉強をしにくいことも挙げられます。
資格学校
資格学校は講師等から直接、指導を受けられるので高い学習効果が期待できます。分からない問題があれば、その場で質問できるのでスムーズに勉強を進めることができるのも資格学校のメリットです。
デメリットは授業時間などが決められているので、自分のペースで勉強ができない点です。カリキュラムに従った方が楽という人にはメリットになりますが、窮屈に感じる人もいるでしょう。この他には、受講する場所まで通学する必要があることや、通信講座よりも費用が高額になることもデメリットに挙げられます。
まとめ
120分という試験時間は長く感じますが試験では、あっという間です。
特に近年の宅建試験では、問題文や選択肢の長文化により時間が足りずに解答できなかったという方も多く見受けられます。本記事を参考に時間配分を意識して試験に挑みましょう。
試験への不安があれば、日建学院の宅建試験対策講座をチェックしてみてください。
受講生のレベルやスタイルに合わせた複数の講座を用意しているので、効率よく勉強することができます。
模試だけ受験することも可能なので、お気軽にご相談ください。