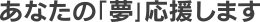宅建試験の合格に必要な勉強時間とは?
社会人が勉強時間を確保する方法を解説!
宅建試験に合格するには、1年間で約300時間から400時間の勉強時間が必要だといわれています。
「仕事をしながら宅建試験に合格できる?」
「スケジュールはどうやって立てる?」
忙しい社会人にとって、働きながら勉強時間を確保するのは至難の業でしょう。そこでこの記事では、宅建試験に合格するための勉強時間、科目ごとの勉強時間や配分、社会人が勉強時間を確保し合格する方法について紹介します。
目次
- 宅建試験に合格するための勉強時間
- ■合格するための勉強時間
- ■他の資格との比較
- 科目ごとの勉強時間
- ■権利関係
- ■宅建業法
- ■法令上の制限
- ■税その他
- ■免除科目
- 勉強時間の配分
- ■基本の勉強時間配分
- ■合格するための必要期間
- 社会人が勉強時間を確保し合格するには?
- ■受験のチャンスは年に1回
- ■電車で通勤している場合
- ■車で通勤している場合
- ■効率的な勉強
- ■最新の法令に対応した1冊のテキスト
- ■スキマ時間の利用
- ■スケジュール作成

宅建試験に合格するための勉強時間
宅建試験に合格するためには、勉強時間の確保が必要です。不動産業界で働いている場合は基礎知識があるため、勉強時間は短くても合格できる場合がありますが、未経験の場合は一定期間の勉強時間が必要になります。ここから合格に必要な勉強時間について解説します。
合格するための勉強時間
近年の宅建試験に合格するためには、300~400時間程度/年間の勉強時間が必要です。未経験者の場合、勉強開始の時期は4月が望ましいでしょう。勉強時間が1日2時間だとすると、約半年間で360時間の勉強時間が確保できることになります。一方、既に他の資格で民法などの法律を学んだ方は、その部分の勉強を省略することもできるでしょう。自身の経験の有無に合わせるとともに、試験日から逆算した必要な勉強時間の確保をおすすめします。
他の資格との比較
宅建士と他の資格の勉強時間を比べてみましょう。賃貸不動産経営管理士は150~200時間、管理業務主任者は200~300時間、マンション管理士は400~500時間の勉強時間が必要と言われています。マンション管理士は、宅建士より多くの勉強時間が求められます。最初に取得する資格として宅建士は適切で、取得後に他の資格も取得し、ダブルライセンスを目指す方法もあります。
科目ごとの勉強時間
合格するためには科目ごとの勉強時間の配分を考える必要があります。ここから、勉強時間を300時間とした時の科目別時間配分について詳しく見ていきます。
権利関係
「権利関係」は民法を中心に出題数が多い科目です。民法の条文だけではなく判例の正確な理解も必要です。丸暗記することは難しく、全体感を把握するのにも時間がかかるため、基本的な項目を押さえ約90時間の勉強時間を目安としましょう。
宅建業法
「宅建業法」は出題数が20問と最も多く、最重要科目です。受験生によっては満点を取る人もおり、しっかりと勉強しなければならないでしょう。過去問を大量に解く必要があるため、権利関係と同様に約90時間の勉強時間を目安としましょう。
法令上の制限
「法令上の制限」は、出題数が権利関係や宅建業法ほど多くはありません。しかし専門用語や覚えなければいけない数値等が多く、理解するのに時間がかかります。法令の根拠を理解するために反復演習を中心に、約80時間の勉強時間を目安としましょう。
税その他
「税その他」は、税金関連について問われます。難易度が高い出題が多いため、深掘りはせず基本的な仕組みや法改正点を中心に、約20時間の勉強時間を目安としましょう。
免除科目
免除科目は統計問題などが出題されます。出題範囲が非常に広いですが、一般常識で判断できる出題も多いため、過去問を中心に約20時間の勉強時間を目安としましょう。
日建学院ではその年度の法改正点や統計データを集めた改正法セミナーを実施しています。ぜひ参加いただき、効率的に学習を進めてください。
勉強時間の配分
宅建試験の科目別勉強時間を見てきましたが、勉強時期に応じた時間配分についても見ていきます。
基本の勉強時間配分
宅建試験の勉強時間は「4~7月の基礎力を蓄える時期」と「8~10月の演習対策をする時期」の2つに分かれます。
4~7月
「4~7月の基礎力を蓄える時期」は、最新の法改正に対応したテキストをしっかり読んで、法令の成り立ちや意味を理解することが重要です。この時期に基礎固めができないと、直前期の演習で誤った暗記に繋がってしまいます。また、テキストを読むだけではなく、過去問も解いてみましょう。間違った問題は復習し、理解できない点をゼロにします。勉強時間は140時間確保しておきましょう。
8~10月
「8~10月の演習対策をする時期」は、問題演習を中心に暗記重視の期間です。暗記を定着させるためには、演習問題や過去問を繰り返し解くことが重要です。勉強時間は160時間確保しておきます。基礎力を蓄える時期に理解した部分を、演習を繰り返すことによって確実な得点源とします。そのため「直前期に演習対策をする時期」の方が「基礎力を蓄える時期」より勉強時間も必要になります。
合格するための必要期間
合格するために必要な期間は半年間から3ヵ月間と言われています。それぞれについて具体的に見ていきます。
半年
宅建試験は10月にあります。そこから逆算すると無理のない勉強時間の確保のためには、4月から勉強を始めることが良いでしょう。半年間(180日間)あるので、1日に2時間勉強すれば、合格に必要だと言われている300時間から400時間を確保することができます。ただし、平日は仕事で勉強時間が取れない場合、平日の勉強時間を1時間に設定し、休日に8時間程度取るなどの時間配分調整が必要です。
3ヵ月
3ヵ月間といった短期間でも合格するのは不可能ではありません。しかし、期間が短い分、1日あたりの勉強時間確保が重要になってきます。合格するためには1日平均3時間以上の勉強時間確保が必要です。7月から10月の仕事量なども想定し、計画的な勉強時間を取るようにしましょう。
社会人が勉強時間を確保し合格するには?
忙しい社会人が勉強時間を確保し、合格するには勉強時間の確保を工夫する必要があります。受験のチャンスは年に1回であり、効率的な勉強が必要です。スキマ時間を使って勉強時間を確保すれば、合格に必要な勉強時間はクリアできます。ここからは社会人が合格するためのポイントについて具体的に見ていきます。
受験のチャンスは年に1回
宅建の受験のチャンスは年に1回だけです。不合格になると精神的なショックだけでなく、次回の試験日まで待つという大きなストレスがかかります。「チャンスは年に1回」であることを頭に入れておきましょう。特に合格者と不合格者で差のつきやすい宅建業法や法令上の制限は、重点的に勉強する必要があります。
電車で通勤している場合
電車で30分かけて通勤している場合、往復の電車で1日に約1時間の勉強時間が確保できます。通勤時間を勉強時間に充てた場合、自宅での勉強時間を減らすことも可能です。テキストや動画配信を使い、効率的な勉強をしましょう。
車で通勤している場合
車で通勤している場合、テキストなどでの勉強はできないため、音声データを利用しましょう。ラジオや音楽ではなく宅建の勉強時間に充てると、効率的な勉強ができます。運転時間を30分とすると、往復の車の運転時間で1日に約1時間の勉強時間を確保できます。帰宅後の1時間は、通勤中に学んだことの復習をしましょう。インプットとアウトプット両方できるため、学習も捗ります。
効率的な勉強
合格するためには効率的な勉強を心がけましょう。宅建試験は暗記しなければいけない項目も多いですが、覚えておくだけで点数が取れるものもあります。ただし、近年の宅建試験では、法令の意味を理解せずに丸暗記だけだと解けない問題も多く出題される傾向があるため、法令の内容を理解することを意識しながら、優先順位を付けて勉強しましょう。
最新の法令に対応した1冊のテキスト
何冊ものテキストに手を出すより、最新の法令に対応した1冊のテキストを繰り返し読み込んだ方が効果的です。難解な項目などは、理解するのに苦労しますが、全てを覚える必要はありません。落としてはいけない問題を落とさないように繰り返し勉強することが重要です。
スキマ時間の利用
社会人が合格するためにはスキマ時間の利用が必要です。例えばスマホを使い、動画講座を視聴したり、聴いたりするだけでも効果があります。通勤時間や家事の合間にも勉強できるため、モチベーションの維持にも役立ちます。
スケジュール作成
宅建試験合格を目指すのであれば、試験日から逆算したスケジュールを作成しておきましょう。スケジュールを作る場合、現実的に実行できるようにしなくてはなりません。また、予定変更できるよう余白期間を作ることも重要になります。スケジュールを作成するには下記の設定が必要です。
ゴール
自身でゴールの設定を可視化することでスケジュール作成がスムーズに進みます。
勉強時間
上述したように、宅建試験に合格するためには、1日平均で約2時間の勉強時間が必要です。2時間をどのように割り振るか、自身で決めておきましょう。
勉強内容
宅建試験の出題範囲は多岐に渡ります。科目ごとに学習期間を定めて無駄のないスケジュールにしなくてはなりません。
勉強期間
宅建試験の勉強時間の配分は、長期スケジュールにするのか、短期スケジュールにするかで異なります。自身がどの勉強期間にするのかを考えて、スケジュールを立てておきましょう。
実行時間の棚卸し
スケジュールを作成しても実際にスケジュール通りに勉強できるとは限りません。自身の一日の動きを見て、勉強できる時間を棚卸しする必要があります。
机で勉強できる時間を作る
社会人は外で働いているため、自宅で机に向かって勉強する時間を確保するのが容易ではありません。自身で勉強時間を意識的に作る必要があります。

まとめ
社会人が宅建試験に合格するには仕事の調整や勉強時間の確保などの工夫が必要です。宅建試験は年に1回しかチャンスがなく、失敗すると精神的なショックやストレスを抱えることになります。一度で合格するためには、勉強時間を効率的に配分できるようスケジュールを立てる必要があります。自身の経験などを踏まえて計画的に勉強期間の設定をしましょう。
日建学院では皆さまのスタイルに合わせた効率的な対策講座を用意しています。ぜひ一度チェックしてみてください。