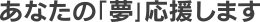宅建試験を独学で合格にするには?
勉強方法・おすすめテキストを解説!
宅建試験合格を独学で目指すと考えた時に、学習を進める全体像が見えていないと、試験勉強を思ったように進められないケースや、過去問を解いても合格点に届かないケースが多く発生しています。そのため本記事では、学習のスケジュールや科目別の学習方法等を丁寧に解説しています。是非最後まで読んでみてください。
目次
- 宅建試験に独学で合格するには?
- ■科目別の配点を確認する
- ■科目の優先順位をつける
- ■スケジュールを作る
- ■苦手分野を作らない
- ■暗記だけでなく理解する
- ■細かいところを気にしない
- 独学での宅建勉強方法
- ■最新の参考書を購入する
- ■4科目の特徴を知る
- ■とにかく過去問を3回解く
- 宅建試験の時期別勉強内容・時間配分
- ■7月
- ■8月
- ■9月
- ■10月

宅建試験に独学で合格するには?
宅建試験に合格するためには、独学で学習する、スクールに通う、など様々な方法があります。どのような選択肢を取るにしても、宅建の学習を進めるうえで、まずどのような試験なのかを自分なりに把握しておく必要があります。
ここでは、下記の6項目に関して詳細に説明し、宅建試験を独学で合格できるようなポイントをアドバイスいたします。
科目別の配点を確認する
まずは、宅建の試験科目の全容を理解しましょう。宅建試験には大きく4つの試験科目があり、「権利関係(民法)」「法令上の制限」「宅建業法」「税・その他」となっています。いずれにしても日常生活では触れることのあまり無い分野が多い試験です。
試験概要は、四肢択一式(50問)によるマークシート方式で、合格には70%程度正答することが必要になります。つまり50問中35問程度は正答する必要があるのです。しかし、上記4分野が同じ割合で出題されるわけではありません。例年、下記の配分で出題されています。
| 試験科目 | 問題数 |
|---|---|
| 権利関係(民法等) | 14問 |
| 法令上の制限 | 8問 |
| 宅建業法 | 20問 |
| 税・その他 | 8問 |
上述の配分の通り、宅建業法と権利関係に関しては問題数が多く、重点的に学習することが重要になります。特に宅建業法は専門的な要素も多く、学習に時間を要するパートではありますが、ここを強みに出来ると宅建試験は一気に合格の可能性が見えてきます。
科目の優先順位をつける
効率的に学習するためには、学習科目に優先順位を付けましょう。
1)権利関係(民法)は、14問出題され宅建業法に次いで出題数が多いです。法律に関する知識が全くない場合は非常に苦労しますが、全ての科目の受け皿となる科目ですので、この科目を捨ててしまわないようにしましょう。
2)法令上の制限は、8問出題されます。暗記すべき内容が多いので、図や表を使ってイメージしながら学習するようにしましょう。また、法改正点などは必ず出題する傾向にあります。
3)宅建業法は、出題数が20問と最も注力するパートになっています。手続き関連や業務上の規制についてなどの実務上の出題が基本となり、暗記項目も多いため過去問を用いて高得点を狙いましょう。
4)税・その他(5問免除科目含む)は、8問出題されます。土地や建物に関係する統計データからも出題されるので過去問を解きつつ、最新の統計データなどを入手しておきましょう。
必ず出題される改正点や統計データなどは日建学院の改正法セミナーでマスターしましょう!
スケジュールを作る
宅建試験は、毎年10月の第3日曜日が試験日となっています。合格に要する学習時間の目安は300~350時間/年間と言われています。社会人が仕事と並行して学習時間を確保するのは3時間/日(20時間/週)が限界だと思います。たとえ3時間/日の学習時間をキープしても、約3.5カ月程度かかります。そのため、申込時期の7月から学習を始めた場合は、1日3時間の学習時間でギリギリ合格できるかという試験になっています。
仕事やプライベートの時間を確保しつつ、合格に必要な学習時間を確保するために、試験日から逆算した無理のない毎日の学習スケジュールを立てましょう。
苦手分野を作らない
試験科目は、4科目あるため苦手分野や得意分野が必ず出てきます。合格のために絶対にやってはいけないのが、1科目を丸々学習しない方針です。
このような穴を作ってしまうと、万が一得意分野で難解な問題が多数出た場合、苦手分野でカバーしきれず、合格は遠のきます。学習を進めるうえで「苦手分野の穴」は作らないように広く学習を進めましょう。
暗記だけでなく理解する
10年ほど前までの宅建試験は「暗記さえしておけば合格できる」試験でした。しかし近年では、問題が長文化し複数の論点の出題や、その法令が設定されている意味や目的を理解していないと正解できない問題の出題などが増えてきました。
近年の宅建試験は、法令の文言や数値など暗記しなくてはいけない部分も多くありますが、それだけでは合格することが難しい試験になってきています。特に宅建業法などの重要科目については、その法令が設定されている意味や目的は何なのかなどを理解することによって、暗記もしやすくなります。重要な論点や試験に頻出する項目は、暗記だけに頼らず理解することも並行して学習を進めましょう。
細かいところを気にしない
納得できないところや頭に入らないパートがあると思います。上述の通り、得意分野のみ学習せず広く学習することを意識して、細かいところでつまずいても必要以上に時間をかけずそのまま学習を進めるようにしましょう。一度わからなかったところはメモをしておき、試験までに解決するなどして、途中で立ち止まってしまわないようにすることが大切です。
独学での宅建勉強方法
最新の参考書を購入する
独学で学習する場合は、まずは必ず最新の参考書を購入するようにしましょう。法改正が行われるとその部分は出題されるケースが多いですが、最新の法改正点は過去問題がなく、かつ、知っているだけで比較的簡単に正解できることが多いため、最新の法改正点をカバーするために最新の参考書が必要になります。
その上で、何が書いてあるのか全体像を把握するために1周通して学習しましょう。全体像を把握できた後は、重要論点の理解を中心に、1周目よりも時間をかけて2~3周は学習するようにしましょう。
日建学院のオススメ参考書:
どこでも!学ぶ宅建士基本テキスト2025年度版
4科目の特徴を知る
権利関係(民法)
宅建業法の次に出題数が多いとともに、宅建試験の全ての知識のベースとなる部分になるので、疎かにできないパートになります。民法に関する知識と裁判例などの正確な理解が求められます。日常生活の中で聞いたことの無い言葉ばかりで非常に苦労すると思いますが、参考書を通して初見の単語をなるべくなくすようにしましょう。
権利関係は学習すべき範囲が最も広く、また、難度も高いため、出題傾向を十分に分析して、やることを充分に絞り込んで学習を進めましょう。また民法がベースとなる科目ですので、「理由を考えながら学習する」ことを心がけましょう。
法令上の制限
ここを苦手にする人が多いパートです。理由は、法律関係の専門用語が非常に多いことが原因です。「第一種低層住居専用地域」「2項道路」「仮換地」等など日常生活で聞いたことの無い単語や用語を淡々と学習する必要があります。
非日常的で専門的な用語が多用されている科目のため、やむを得ないといえますが、条文に忠実な出題が多いことから、ある程度まで学習をすると実は得点しやすい分野になります。ご自身の身の回りの地域などに「第一種低層住居専用地域」などを当てはめて、効率的に学習しましょう。
宅建業法
宅建業法は、20問の出題となっており、全体の40%を占める超重要科目です。宅建試験の合格者の多くは、この科目で点数を稼ぎます。免許の欠格事由や重要事項の説明に関して、宅建士の独占業務などが関わる非常に重要な項目ですので、点数を稼げる得意パートに出来るように何度も学習しましょう。
近年の出題内容を見ても、例年、2~3問程度の難問はありますが、それを除けば、必ず得点が可能な出題ばかりです。 したがって、テキストの読み込みや過去問の繰り返しの演習のほか、類似の規定同士を比較した横断的な学習など、穴のない学習を心がけましょう。
税・その他
税・その他のパートでは、専門的だったり広範囲の知識が必要だったり、非常に学習が難しい分野です。
そのため、独学で効率的に学習する場合は、税制の法改正や最新の統計情報などを押さえておくことが非常に重要です。法改正があると出題されることが多いため最新のトレンドを押さえるようにしましょう。
とにかく過去問を3回解く
最新の参考書でざっと学習した後に、実際に過去問を解いてみましょう。ここで近年の出題形式や問題の問われ方などを把握することが出来るため、どのような項目に注力して学習すればよいのか、自身の得意不得意分野はどこなのかが見えてきます。
また、近年の宅建試験は過去の宅建試験と比べると、問題文や選択肢が長文化傾向にあるとともに、単純な暗記で回答できる問題が減り、何を問われているかの問題文自体の文章を理解・整理する必要がある出題が増えています。そのため、単純に過去問を解くだけではなく「この問題文はどの法令の問題なのか」「実際の業務(重要事項説明など)ではどのような内容なのか」などを想定しながら解くようにしましょう。

宅建試験の時期別勉強内容・時間配分
ここでは独学で3.5カ月間の最短学習期間で合格するための勉強内容・時間配分を紹介します。3.5か月前からのスタートとなるため、1日の学習時間は約3時間の確保が必要です。1日の学習時間を確保することが難しい場合は、週末に挽回するなどで1週間に約20時間の学習時間を確保できるようにしましょう。
7月
まずは初旬に受験申込を済ませます。そして最新版の参考書を購入しましょう。最初の1週間で参考書全体を包括的に読み込んで、宅建の全体像を把握しておきます。
その後2週間程度かけてじっくり全体的に勉強をするようにしましょう。ここでは焦らずに試験の全体像と専門用語の初見を無くすことを目的にしてください。過去問を解いた時に、「こんな言葉は知らない」という学習意欲がなくなってしまう現象を起こさないようにすることが大切です。
8月
8月からは昨年の過去問を解いてみましょう。過去問を解くことで出題形式や学習の方向性を確認できます。
8月は1年分の過去問で高得点を取れるように徹底的に学習します。ここでは分からないところを無くすということを意識しましょう。1年分の過去問を徹底的に理解し、分からないところを無くすことで今後の学習に繋がっていきます。また、徹底的に過去問演習を繰り返すことによって科目の全体像を一度理解している状態を作ることができます。
9月
9月は過去2~3年分の過去問を解いてみましょう。最新の参考書を用いて各法令を理解しつつ、暗記が必要な部分は徹底的に暗記して高得点を取れるように学習しましょう。
また、間違った問題は都度参考書等を確認して、各法令や間違っている根拠を徹底的に確認するようにしましょう。直前期のこの時期に、繰り返し各法令の理解を進めることで、本試験に向けた完璧な状態を作ることが出来ます。
10月
10月に入ったら体調管理に注意し、重要項目を中心に再度の復習をしましょう。また、最新情報(法改正の有無)や最近のトレンドをチェックしつつ、本試験慣れする為に講習機関の模擬試験なども受験してみましょう。日建学院では最後の実力確認に最適な「宅建全国統一公開模擬試験」を実施しています。合格に向けて万全の準備のために、ぜひ受験してみてください。
まとめ
宅建試験を独学で乗り切るための工夫は理解できましたでしょうか?
宅建試験に独学で合格するには、まず学習時間の確保が重要です。そのうえで科目別の配点を確認し、科目の優先順位をつけることが必要です。参考書の重要項目を理解するとともに必要な部分は徹底的に暗記し、過去問を何回も繰り返し解くことで、独学での合格が見えてきます。
万遍なく学習することで得意不得意が分かってくるため、どんな年の試験であっても合格点を超えられるように学習を進めていきましょう。
日建学院では皆さまのスタイルに合わせた効率的な対策講座を用意しています。ぜひ一度チェックしてみてください。