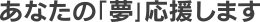【2026年度最新】宅建試験の宅建業法攻略法を分かりやすく解説。
近年の傾向と学習ポイントもご紹介!
- ・「宅建試験の宅建業法ってどんな科目?」
- ・「宅建業法で高得点を目指すには?」
という疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、そんな疑問の解決に役立つ内容を、
- ・宅建試験における宅建業法について
- ・宅建業法の攻略ポイント
- ・宅建業法の全体構造と学習方法
の順番に解説していきます。
宅建士資格取得を目指している人には役立つ記事になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 宅建試験における宅建業法について
- ■宅建業法の傾向分析・得点目標
- 宅建業法の全体構造と学習方法
- ■宅建業法の「意義」
- ■宅建業の免許・宅建士(宅地建物取引士)・保証金
- ■業務上の規制
- ■監督・罰則
- ■住宅瑕疵担保履行法

宅建試験における宅建業法について
国家資格である宅建士資格を取得するには、宅建試験に合格する必要があります。
宅建試験は、「権利関係」、「宅建業法」、「法令上の制限」、「税・その他」の4科目で構成されており、中でも「宅建業法」は、出題数が多く最重要な分野です。宅建業法の正式名称は「宅地建物取引業法」と言います。宅地建物取引業法とは、顧客に不利がないように適切な不動産取引を担保するために定められたルールのことです。
以下で、近年の宅建業法の詳細について確認していきましょう。
宅建業法の傾向分析・得点目標
出題数が20問であり、50問中4割もの出題数を占める宅建業法は、まさに、"合格のカギを握る"科目です。そのため、ここで5問以上ミスしたら、『取り返しは不可能』と考えてもよいほどです。
日建学院独自の調査データによると、過去12年間の本試験での「宅建業法」分野・出題全体の平均正答率は「約65%」であり、かつ、各テーマ単位での平均正答率も、ほぼすべてで60%超でした。それはつまり、宅建業法出題全般で、まんべんなく手堅く得点されているということです。
また、出題内容を見ても、例年、2~3問程度の難問はありますが、それを除けば、必ず得点が可能な出題ばかりです。 したがって、テキストの読み込みや過去問の繰り返しの演習のほか、類似の規定同士を比較した横断的な学習など、学習方法のバリエーションも検討して、穴のない学習を心がける必要があります。
宅建業法は合格のカギを握る分野ですので、宅建試験合格のためには、20問中18問以上の得点目標が必要です。以下で各項目の"攻略ポイント"を解説します。
宅建業法の攻略ポイント
用語の定義・免許制度
「用語の定義」は、事例形式で「宅建業とは何か」を問うものが定番ですので、過去問で出題形式に慣れておくことが大切です。
「免許制度」では、免許の基準・免許換え・変更の届出・廃業等の届出が頻出事項です。なお、「免許の基準」は、宅建業法前半の"ヤマ"といえる部分です。細かい規定がありますが、出題されやすい部分は比較的限られていますから、テキストと過去問を連動させて使用すれば、効率よく学習することができます。
宅建士制度
「登録」と「宅建士証」に関し、変更の登録・登録の移転・死亡等の届出・宅建士証の交付といった手続関係の規定が、出題のポイントです。
「宅建業者に勤務する宅建士」という場面設定で、免許制度と宅建士制度の両方に対する理解度を確認する問題が多く見られますので、こういった出題形式に対応できるよう、常に関連づけて理解しておく必要があります。
保証金制度
「営業保証金」と「保証協会」から毎年1問ずつ出題されています。いずれも、供託と還付に関する手続がポイントになります。両者は、消費者の救済という同じ目的を持つ制度でありながら、手続の流れ等に異なる点がありますので、混乱しないように対比しながら学習してください。
業務上の規制
業務上の規制では、3大書面、8種制限及び業務上の諸規制から、例年全部で10問以上と大量に出題されています。
「3大書面」は、重要事項説明書等を「いつ・誰が・誰に対して・何を」という視点でまとめておくことが大切です。特に、「何を」に該当する書面記載事項は暗記すべき点が多く、宅建業法の"難所"ともいえるところです。
「8種制限」は比較的出題が多い項目の1つで、学習のヤマです。これに対し、業務上の諸規制は、難度そのものは高くありませんので、1つ1つ丁寧に学習して、確実な得点を目指しましょう。
報酬・監督処分
「監督処分」は、宅建業法の中ではやや優先順位が落ちる項目といえますが、ケアレス・ミスは許されません。
「報酬」は、計算問題が最も多い出題パターンですから、消費税が関与した報酬計算の方法をしっかり練習しておきましょう。また、「監督処分」は、処分の種類とその特徴をまず押さえたうえで、学習の進捗状況に応じて知識の上積みを考えていく必要があります。
宅建業法の全体構造と学習方法
宅建業法の「意義」
土地・建物などの不動産は、とても価値の高い財産です。また、取引にともなう手続は複雑でわかりにくく、不動産に関する知識の少ない一般消費者と、"その道のプロ"である宅建業者が公平な立場で取引をするのは大変困難です。
そこで一般消費者を、不動産の取引を安全にできるように保護するために、宅建業者を規制し、監督するための法律が、宅建業法です。
宅建業の免許・宅建士(宅地建物取引士)・保証金
宅建業法は、「①宅建業の免許・②宅建士・③保証金」という3つの大きな"基本の仕組み"を規定しています。
①宅建業の免許
免許制度は、一般消費者からみて「この業者は安全な取引をするために十分な資質がある」とわかるようにするもので、宅建業者に対して「免許=宅建業を営む資格」を与え、一定期間ごとに免許の「更新」をさせることで、その宅建業者の安全性の再確認をしています。このような免許制度によって、宅建業法は、全国にたくさんある宅建業者を取り締まっています。
②宅建士
宅建業者に「免許」を与える以上、その業者には、不動産取引に関する専門的知識が備わった者の存在が必要です。そこで、「宅地建物取引士」(宅建士)という不動産取引の専門家の設置を宅建業者に義務づけています。
③保証金
高額な不動産取引で、一般消費者に不測の損害を与えてしまった場合に備えて、その損失を補填するために、一定額の営業保証金を供託するか、または保証協会に加入するか、いずれかの方法をとらなければなりません。それが、「保証金」という制度です。
これらの3つの制度によって、「専門的知識と資力の両方が担保された宅建業者」を実現させ、不動産取引の安全を図っています。
業務上の規制
宅建業者の業務は、大きく分けると次の流れになりますが、各段階で、宅建業法はさまざまな「業務上の規制」を課しています。

①広告の規制
物件を一般消費者に対して販売しようとする際には、まずは広告をするのが一般的です。実際よりも誇大な広告は、一般消費者を誤解させるおそれが高いため、禁止されています。また、未完成物件の広告は、少なくとも建築確認などの許可等を受けた後でなければ、行うことができません。
②媒介契約の規制
宅建業者が一般消費者から、不動産取引の仲介の依頼を受けることを、媒介契約といいます。この媒介契約に基づいて成約した場合、宅建業者は、依頼者から報酬の受領ができるため、媒介契約の内容は書面にして、受け取る報酬に関する事項等、一定の事項を記載しなければなりません。
③重要事項の説明
契約をした後に「こんなはずじゃなかった……契約破棄だ!」というようなトラブルを回避するための、大事な手法です。
宅建業者は、売買や賃貸借といった不動産取引が成約するまでに、その物件を手に入れようとする買主・借主に対して、物件が置かれている物理的状況や権利関係等を、書面を交付する等して、宅建士に説明させなければなりません。ちなみにこの重要事項説明書は宅建業法の35条で定められているため、「35条書面」とも呼ばれます。
④37条書面の交付
宅建業者は、不動産取引が成約したときは、遅滞なく、契約の内容となる一定の事項を記載した契約書(37条書面)を作成し、契約当事者(売主、および買主等の両者)に交付する等しなければなりません。
重要事項説明書とは異なり、37条書面に関する説明は宅建士でなくても行うことができます(説明は必須ではありません)。
⑤8種制限
宅建業者が自ら売主となって、一般消費者に宅地・建物を売却する場合、両者の"力関係"を修正するため、宅建業者に特別に課せられた8種類の規定があります。
一般消費者が一定期間、契約を「白紙撤回」することができるようにするためのクーリング・オフ制度や、受領した手付金等が一定額を超えた場合に、一般消費者に返還できるようにしておく保全措置等が、これにあたります。
⑥報酬規制
無事に不動産取引が成約した場合、宅建業者は依頼者から報酬を受け取ることができますが、この金額には、その取引が売買か賃貸借か、また、宅建業者の取引態様が媒介か代理かといった違いによって、それぞれ上限が定められています。なお、宅建業者は、たとえ依頼者の好意によっても、この上限を超える金額を受領することはできません。
⑦諸規制
「取引に関与したことによって知り得た秘密を漏らしてはならない」とする守秘義務や、帳簿・標識の設置義務など、上述の①~⑥に付け加えて、その他宅建業者に対する規制が「諸規制」として、きめ細かく定められています。
監督・罰則
数多く設けられた規制の実効性を担保するため、違反した宅建業者には、免許取消処分や業務停止処分といった監督処分が規定されています。さらに、罰金や懲役といった刑罰まで規定することによって、違反行為の防止を図るとともに、違反者に対する取締りをしています。
住宅瑕疵担保履行法
平成17年に大きな社会問題となった「耐震偽装事件」を契機に、新築住宅に一定の欠陥があった場合の売主の損害賠償責任の履行を確実にするための措置が求められ、その要請に応えて平成19年に新たにできた法律で、平成22年度より、宅建業法における「関連法令」として、毎年1問出題されています。
なじみのない用語が多いものの、内容的にはさほど難解ではありません。過去の出題を主軸として、その関連知識をきちんと押さえておけば、対策は充分です。
\\本試験問題にチャレンジ//
令和6年度宅建試験 第39問 案内所等の届出
<正答率67.2% ※日建学院調べ>
宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
1 届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。
3 届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。
4 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。
------------------------
1:正しい 契約行為等を行う事務所以外の場所→1人以上の専任の宅建士の設置が必要。
2:正しい 土地に定着する契約行為等を行う案内所→クーリング・オフ制度の適用除外。
3:正しい 売主業者も案内所等で申込みを受ける→売主業者も届出が必要。
4:誤り 免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事にも届け出る。
------------------------
ワンポイント解説
宅建業法は各問題とも正答率が高いのが特徴で、差が付かないことも多いのですが、本問は合格者と不合格者の正答率が39%と大きく差が付いた問題でした。案内所等関係は、きちんと学習が進んだ人とそうでない人との力の差が出やすい項目です。
宅建業法で満点を狙う攻略法
宅建業法の条文の数はさほど多くはなく、しかも中には出題実績がまったくないものもあるので、マトを絞ってマスターするのはさほど難しくありません。学習にかけた時間に応じて理解も深まりやすいため、できれば1~2問程度のミスにとどめておけるよう、万全を期した慎重な学習が必要です。

特に、「免許と宅建士」や「営業保証金と保証協会」「重要事項説明書と37条書面の記載事項」のように、異なっていながら類似する規定が多々ありますから、それらを混同しないよう、「比較しながら理解し整理する」ことが肝心です。そのうえで、関連する過去問などを通じて、宅建試験の出題形式などにしっかり慣れておくことが必須といえるでしょう。
まとめ
今回の記事では、宅建試験における宅建業法について、宅建業法の近年の傾向分析、攻略ポイント、宅建業法の全体構造と学習方法について解説しました。
宅建試験において、宅建業法からは多くの問題が出題されます。過去問から出題されることが多いので、しっかりと対策をして高得点を狙いましょう。
日建学院では、宅建試験向けのさまざまなカリキュラムをご用意しており、一人ひとりに合わせたコースで学習を進めることができます。一人で学習を進めることが不安という人は、日建学院の宅建講座をチェックしてみてください。