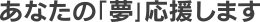【2026年度最新】37条書面の覚え方は?
記載事項や重要事項説明書(35条書面)との違いも一覧で解説!
宅建試験で毎年複数問出題される「37条書面」。この37条書面について、37条書面の記載事項が覚えられない、重要事項説明書(35条書面)との違いは何?という方も多いと思います。
本記事では、そんな疑問の解決に役立つ内容を
- ・37条書面の概要や記載事項について
- ・重要事項説明書(35条書面)と37条書面の違いを一覧でご紹介
- ・37条書面の覚え方のコツ
の順番に解説していきます。
2024年度も37条書面に関して3問出題されました。2026年度の宅建試験に挑戦する人には役立つ記事になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
- 37条書面の記載事項一覧
- ■絶対的記載事項
- ■任意的記載事項(定めがあれば必ず記載)
- 37条書面が覚えられない?覚え方のコツ
- ■テキストを繰り返し読み込み過去問を解く
- ■毎日条文に触れる
- ■場面をイメージする
- ■覚え歌で覚える

37条書面とは
37条書面とは、不動産の契約を結んだ際に宅建業法に基づき交付が義務付けられている書面です。
不動産契約は、内容や権利関係が複雑であり、37条書面は契約後の契約内容に関する争いを防ぐために存在します。37条書面の内容は、法律で定められており、契約の当事者の氏名・住所や物件情報、建物の状況、代金、支払い方法、引渡し時期、登記の申請時期などが含まれます。また、損害賠償や違約金に関する事項、不可抗力による損害負担なども記載が必要です。
重要事項説明書(35条書面)と37条書面の主な違いですが、重要事項説明書(35条書面)は宅建士による説明・交付が必要ですが、37条書面には説明義務はなく、宅建士以外の従業員でも説明・交付できます。
37条書面の記載事項一覧
37条書面には、必ず記載しなければいけない 「絶対的記載事項」、定めがあった場合に記載すれば良い「任意的記載事項」に分けられます。
以下に、絶対的記載事項と任意的記載事項の一覧を「売買・交換」と「貸借」に分けて一覧でまとめました。
絶対的記載事項
| 絶対的記載事項 | 売買・交換 | 貸借 |
|---|---|---|
| 当事者の氏名・住所 | ○ | ○ |
| 物件を特定するために必要な表示 | ○ | ○ |
| 既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について双方が確認した事項 | 〇 | × |
| 代金(売買)、交換差金(交換)、借賃(貸借)、支払時期、支払方法 | 〇 | 〇 |
| 物件の引渡し時期 | 〇 | 〇 |
| 移転登記申請の時期 | ○ | × |
任意的記載事項(定めがあれば必ず記載)
| 任意的記載事項 | 売買・交換 | 貸借 |
|---|---|---|
| 代金以外に発生した金銭の額、授受目的など | ○ | ○ |
| 契約解除に関する事項 | ○ | ○ |
| 損害賠償や違約金について | 〇 | ○ |
| 代金または交換差金についてローンの斡旋が不成立の時の措置 | 〇 | × |
| 天災など不可抗力による損害負担 | 〇 | 〇 |
| 担保責任(契約不適合責任)について | 〇 | × |
| 担保責任(契約不適合責任)の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結等の措置 | ○ | × |
| 宅地もしくは建物に関する租税、その他の公課の負担の内容 | 〇 | × |
重要事項説明書(35条書面)と37条書面の違い一覧
不動産取引における、重要事項説明書(35条書面)と37条書面の違いを以下に一覧でご紹介します。
| 項目 | 第35条書面(重要事項説明書) | 第37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| 目的 | 契約前に不動産の重要事項を説明する | 不動産取引の詳細を正式に記録する |
| 交付時期 | 契約成立前 | 契約成立後すぐ(遅滞なく交付) |
| 書面化 | 必須 | 必須 |
| 交付相手 | 買主や借主 | 両当事者 |
| 交付者 | 宅地建物取引業者 | 宅地建物取引業者 |
| 作成者 | 宅地建物取引業者 | 宅地建物取引業者 |
| 説明者 | 宅地建物取引士 | 特定なし(通常は業者・代表者) |
| 記名 | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士(第重要事項説明書と同一でなくてもよい) |
重要事項説明書(35条書面)は、契約前の重要事項の説明に重点を置いており、取引の透明性を確保するためにものです。そのため、作成、説明するタイミングは契約成立前となります。また、説明は、宅建士が実施しなければなりません。
一方で、第37条書面は、契約成立後の取引詳細の正式な記録として作成します。宅建士による記名や遅延のない交付が求められますが、説明義務はなく、従業員が作成・説明しても構いません。
\\本試験問題にチャレンジ//
令和6年度宅建試験 第44問 37条書面
<正答率91.4% ※日建学院調べ>
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
2 Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
3 Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
4 Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。
------------------------
1:違反しない 重要事項の説明時の図書の交付で、特定に必要な表示。
2:違反する 借賃の額・その支払の時期・方法は、必ず記載する。
3:違反する 宅地・建物の引渡しの時期は、必ず記載する。
4:違反する 相手方が承諾をしても、37条書面の交付を省略できない。
------------------------
37条書面が覚えられない?覚え方のコツ
37条書面を覚えるためのコツは、以下が挙げられます。
- ・テキストを繰り返し読み込み過去問を解く
- ・場面をイメージする
- ・書いて覚える
- ・声に出して覚える
- ・覚え歌で覚える
37条書面は普段聞きなれない言葉や法律が多く出てきます。そのため、本項目で紹介する覚え方を参考に、37条書面を覚えていきましょう。
テキストを繰り返し読み込み過去問を解く
最新の法改正に対応したテキストを何度も読み込むことで、37条書面の記載事項を自然と確認でき、記憶に定着させることができます。さらに、過去問を繰り返し解くことで、知識の定着につながるだけでなく、試験の傾向を掴むことができます。
公益社団法人日本心理学会の研究により、繰り返し解く行為は、記憶を定着させる遺伝子の発現を誘発し、長期記憶として定着することが証明されています。「テキストの読み込み」と「過去問演習」を繰り返し実施し、37条書面をしっかりと覚えていきましょう。
参考:短期記憶における視覚記憶と聴覚記憶の差異 (jst.go.jp)
場面をイメージする
また、ただ単純に丸暗記するだけではなく、場面をイメージしながら記憶すると覚えやすくなり、試験時もスムーズにアウトプットができるでしょう。
例えば、重要事項説明書(35条書面)や37条書面の目的や内容を覚える際は、実際に不動産業者から重要事項説明を受けている場面や37条書面の交付を受け、内容を確認している場面をイメージするなどです。具体的な場面をイメージした際、そこに感情を発生させることができると、より記憶に定着させることができます。
これは、情動記憶と呼ばれ、記憶と感情を結びつけるとより暗記力が向上することが証明されていますので、積極的に活用していきましょう。

覚え歌で覚える
最後に、覚え歌で楽しく記憶を定着させる方法もあります。
37条書面の記載事項を覚え歌にした動画や、関連する音声は、インターネット上にも公開されています。自分に合った覚え歌を探して、暗記に活用してみましょう。歌詞を覚えるためにテキストへ書き出したり、自分の声に出してみたりすることで記憶の定着がより早く進むでしょう。
まとめ
37条書面は、不動産取引の正式な契約書として、法律で定められた記載事項を含める必要があります。
また、重要事項説明書(35条書面)とは、目的や交付時期などが異なります。37条書面(契約書)と35条書面(重要事項説明書)を比較して、違いを把握するようにしておきましょう。37条書面は宅建業法の中でも、毎年複数問出題される重要な項目です。なかなか覚えられない、重要事項説明書(35条書面)といつも混同してしまう、という方は一度日建学院までご相談ください。
日建学院の宅建講座は、宅建試験の専門学校として、豊富な教材や講師陣、カリキュラムを提供しています。また、オンラインでの受講も可能で、自分のペースでの学習も可能です。ぜひ、日建学院の公式サイトをチェックしてみてください。