手摺と建具を重ねて入力することもできます。
これを利用して、階段下収納を表現してみます。 |
| |
| |
 階段になる部分に、「物入」を入力し、手摺を入力します。 階段になる部分に、「物入」を入力し、手摺を入力します。
※  (階段入力)−[手摺]コマンドで手摺を入力することが出来ますが、ここでは「物入」の壁を兼ねた手摺を入力するので、 (階段入力)−[手摺]コマンドで手摺を入力することが出来ますが、ここでは「物入」の壁を兼ねた手摺を入力するので、 (手摺)コマンドを使って入力します。 (手摺)コマンドを使って入力します。 |
| |
| |
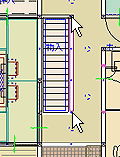 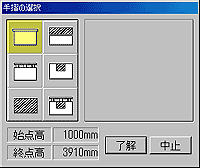 階段の勾配にあわせた手摺を入力します。 階段の勾配にあわせた手摺を入力します。 (手摺)を選択すると、[手摺の選択]ダイアログが表示されます。手摺のタイプを選択し、数値部分をクリックして[始点高]・[終点高]を設定し、[了解]ボタンをクリックします。 (手摺)を選択すると、[手摺の選択]ダイアログが表示されます。手摺のタイプを選択し、数値部分をクリックして[始点高]・[終点高]を設定し、[了解]ボタンをクリックします。
「物入」の壁に沿って入力します。 |
| |
| |
 (重ね記号)を選択します。 (重ね記号)を選択します。
[重ね記号の選択]ダイアログが表示されます。[重ね記号詳細設定]ボタンを選択して[了解]ボタンをクリックします。
先に入力した手摺を指示します。 |
| |
[重ね記号の設定]ダイアログが表示されます。
[追加設定]ボタンをクリックし、重ねる建具を選択します。
ここでは、[内部建具]-[内部折戸・伸縮]-[(折戸)フラッシュ2枚]を選択し、追加します。
追加後、[建具高]・[内法高]・[始点位置]・[記号長]を必要に応じて設定します。
※
[画面表示]にチェックすると、折戸が平面図で表示されます。 |
| |
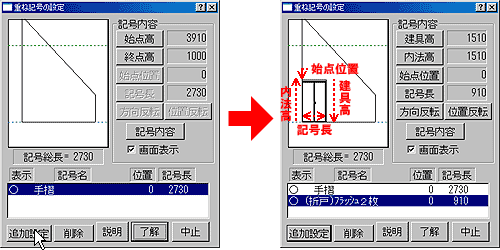 |
|
| |
| |
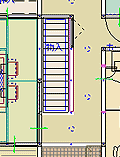 設定が終了したら、[了解]ボタンをクリックします。【鳥瞰図】・【外観立面図】・【パース】などで確認してみましょう。 設定が終了したら、[了解]ボタンをクリックします。【鳥瞰図】・【外観立面図】・【パース】などで確認してみましょう。 |
| |