| Step01で作成したレイアウトフォームを個々に縮尺変更や移動、凡例の入力などをして、レイアウトしていきます。 |
| |
| 性能図面縮尺変更 |
| |
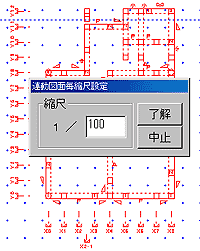 個々のレイアウトフォーム(性能図面)を、縮尺変更します。 個々のレイアウトフォーム(性能図面)を、縮尺変更します。
[性能図面]/[性能図面縮尺変更]を選択します。
縮尺を変更する性能図面をクリックすると、選択した性能図面が赤で表示され、[連動図面毎縮尺設定]ダイアログが表示されます。縮尺部分に数値を入力し、[了解]ボタンをクリックすると、縮尺が変更されて表示されます。
必要に応じて、他の性能図面の縮尺も変更します。 |
|
| |
| |
| 性能図面移動 |
| |
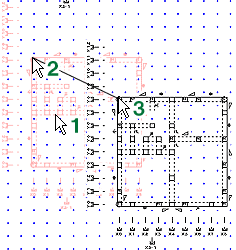 個々のレイアウトフォーム(性能図面)を、移動します。 個々のレイアウトフォーム(性能図面)を、移動します。
[性能図面]/[性能図面移動]を選択します。
移動する性能図面をクリック(図中1)すると、選択した性能図面が赤で表示されます。移動する基準点をクリック(図中2)し、移動先の基準点をクリック(図中3)すると、性能図面が移動されます。
必要に応じて、他の性能図面も移動します。 |
|
| |
| |
| 凡例の入力 |
| |
| 柱・壁伏図の凡例を入力します。凡例は、既に性能図面として登録してあります。 |
| |
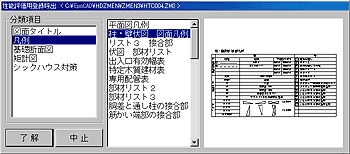 [性能登録]/[性能登録呼出]を選択します。 [性能登録]/[性能登録呼出]を選択します。
[性能評価用登録呼出]ダイアログが表示されます。
[分類項目]から「凡例」、リストから「柱・壁伏図 図面凡例」を選択し、[了解]ボタンをクリックします。 |
| |
[転送ファイル読込情報設定]ダイアログが表示されます。
各項目を設定して[了解]ボタンをクリックします。
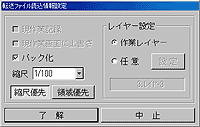
| [パック化] |
− |
性能図面をパック化します。これにより[性能図面]コマンド([性能図面縮尺変更]や[性能図面移動]など)が使用できます。 |
| [縮尺] |
− |
性能図面の縮尺を設定します。
※
[パック化]しておけば、入力後に[性能図面縮尺変更]ができます。 |
[縮尺優先]
or[領域優先] |
− |
他図面を読込んだ場合に、現在の縮尺のままデータ表示させるか、現在の領域のままデータを表示させるかを選択します。 |
| [レイヤー設定] |
− |
性能図面を格納するレイヤーを設定します。 |
|
|
| |
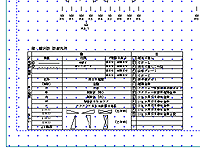 [性能図面]の領域枠が表示されますので、配置する場所をクリックしてレイアウトします。 [性能図面]の領域枠が表示されますので、配置する場所をクリックしてレイアウトします。 |
|
| |
| |
| 加筆修正 |
| |
その他図面枠など、必要な内容を加筆します。
※
図面枠などよく使うものは、[性能登録]で登録しておくとよいでしょう。 |
| |
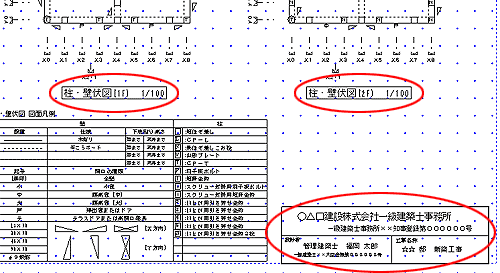 |
|
| |